
沖縄は和名(日本名)、琉球は漢名(中国名)です。
沖縄 → ・外海の船から見たら、沖に縄を浮かべたように見えたから。
→ ・泊村の大里という人が岸辺で釣りをして、その釣縄を置く所が置縄で、これが沖縄の地名になった。
→ ・那覇港入口の沖漁場(オキナワ)から。
琉球 → ・蛟(みずち・竜の子)が水中に浮かんでいるようなものだから琉蛟(りゅうきゅう)と名づけた。
→ ・島の形が海上に浮かんでいる蛟(ミヅチ竜)に似ているので琉蛟、琉球となった。
→ ・魚の国(うよのくに)の発音が、中国人にイユクと聞こえ、ユークーとなり琉球の字をあてた。
ニライカナイ 海の彼方向こうにある、豊かな実りと幸せをもたらしてくれる理想郷。
ニライカナイとは海のかなたの理想郷を意味し、その方角は地域、時代によって大きく変わっていま
す。時には幸せばかりでなく飢餓や病気など凶事も運んでくることがあります。 また神や先祖は時を
定めてニライ(神の世界・あの世)からおとずれると考えられています。お盆には先祖が海のかなたから
帰ってくると考えられる地域もあるようです、そのため沖縄にはウタキ(礼拝所)が岬や海辺に多く見受
けられます。
島尻 → ・島の尻尾(しっぽ)から。
アシビナー → ・村の芸能をする場所から。
アマンチュー森 → ・佐敷町津波古吉原 天人(アマンチュー)が降りたところ。多和田井の近くの石にアマンチュー
の足跡がある。
糸満 → ・昔、外国船が糸満の沖で難破し、八人の乗組員が上陸し、兼城の洞くつに仮住まいした。そこをロンドン
ガマというようになった。外国人は村人と交流しやがて糸満の娘を妻に迎え住み着いた。この人たちが感
謝の意味をこめて、ここをエイトマン(八人の男)と名づけのちにイトマンに変わった。
、
喜屋武 → ・きやめ、しまの最南端という意味から。
白銀岩(堂) → ・ミドンという人が薩摩の武士より借りた金を返せない。怒った武士が、刀に手をかけようとすると『
意地ぬ出じらぁ手引け。手ぬ出じらぁ、意地引け。』(短気をおこしたら、手を出さないようにし、手が出よ
うとしたら、心をしずめよ。)といさめて許しを乞うた。後日、帰国した薩摩の武士、玄関にみたこともない
男ものの履物心中穏やかでない武士が部屋に入ると、妻が男と添い寝ている。武士は、狂わんばかり
に怒り男を殺そうと刀を振り上げた、その時武士は糸満のミドンの言った言葉を思い出し、心を静めて男
をよく見ると、それは男物の着物を着た母親であった、男装して妻に添い寝をしていた母を危うく殺すと
ころを、ミドンの言葉で思いとどまった。武士はそのことのお礼に、ミドンへ貸した金を棒引きにすると申
し出たが、互いに譲り合って、受け取ろうとしない、 そこでミドンはその金を洞窟の中に埋め、お堂を建て
糸満の男達の海上の平安と村の繁栄を祈ることにした。それには、薩摩の武士も大賛成した。この話は
たちまちのうちに沖縄中に広がり、人々はその洞窟を拝むようになり、それからこの洞窟を白銀堂と呼ぶ
ようになった。
粟国島 → ・粟が取れる島から。
渡名喜島 → ・素朴、純情な島人で盗人が昔からなく家は雨戸を必要とせず、いつも、開放して暮らす。雨戸無しの
島、戸無(トナシ)から
→ ・杜那崎、渡名喜となった。
那覇 → ・ナバ(きのこ)の形をした石、奈波から那覇へ。
赤田 → ・赤い田(赤土)から。
一日橋 → ・花城親方が亡くなった時、葬列の通る予定の敷名橋が豪雨で決壊した。王は家来に命じて花城親方
のために、橋を一夜二昼にして修造させ,無事具志頭間切那宇島に葬らせた。一日にして修造したので
一日橋と呼ばれるようになった。
御成橋 → ・那覇市久茂地にかかる橋で、1921年昭和天皇がヨーロッパに行く途中沖縄に立寄り県庁に行く途中
この橋を通ったので「御成り」と名づけられた。
奥武山 → ・昔、城獄に住んでいた豪農の王之親方(オオヌウフヤー)の領分であったため、王之山といわれ、現在
は奥武山の字をあてている 。
ガジャンビラ → ・昔、唐から蚊(ガジャン)を持って来たとき、ここでキッチャキして転び、蚊(ガジャン)が入った虫か
ごを壊してしまい逃がしてしまったため。この蚊(ガジャン)が沖縄じゅうに広がっていった。
十貫瀬 → ・昔、旅人が岩のそばで雨宿りをして、十貫のお金を置き忘れた。数年して、またやってきたが、十貫が
そのままあったのでその地名がついた。
識名 → ・中城村に昔、識名村という小さな村があつた。ある日山崩れで村が全滅した。ひとり生き残ったサンラ
-の前に赤い火の玉が村跡から飛び、それが現在の識名に下りた。そのためサンラーが、そこに 移り住
んで村を建て直した。
天妃町 → ・三六姓が、航海の神として天妃を祀ったのでその一体の地名になった。
繁多川 → ・高い崖のちかくの端の井戸、首里金城町に通ずる識名坂の頂上にある井戸の名が部落の地名になっ
た。ハンタのカー が ハンタガーになった。
美栄橋 → ・新橋(ミーバシ)が美栄橋になった。
明治橋 → ・明治になってから架けられた橋。
天川坂(ウケーメー坂) → 橋のたもとにある天川という井戸から。別名ウケーメー坂ともいうが、これは、1609年、
薩摩軍が押し掛けてきたとき、煮えたぎったおかゆ(ウケーメー)をさかの上から流し坂を上るの
をふせいだという 故事から。
石川 → ・イーフンチャー(堆積した土砂)から石川になった。
浦添 → ・首里城が王城となる以前の王城(浦添城)があったところで、「浦襲う」 浦々を支配する所という意味から
。
大謝名 → ・昔、大謝名の人々は周囲の村々から「ンジャラー」(むつかしい人)と呼ばれていた。ンジャラーがなま
って大謝名になった。
大湾 → ・読谷村大湾。村の北側に大きな湾があったから。
具志川 → ・グシチャー(すすき)の原野から。
古謝 (沖縄市) → ・この一帯の地質がクチャとなっており、クチャより古謝になった。
コザ (沖縄市) → ・古謝からコザ、あるいは胡屋から胡差→コザになった。
田場 (具志川) → ・水の豊富な村で周囲が田んぼだったから。
高江洲 (具志川) → ・江洲村より高いところにあったから。
知花 (沖縄市) → ・地域でもっとも高い土地の突端、すなわち
登川 (沖縄市) → ・池原村から行くときに、池原川を渡って登ったところにあるのでこの地名がついた。
野嵩 (宜野湾) → ・ヌーダキから野嵩、ヌーはヌール(ノロ)、ダキは御嶽のこと。
牧港 → ・源為朝が京都にせめて平氏を打ち破ろうと妻子ともども浦添の港から船出したが伊江島付近にきて急に
暴風が起こり進めなくなった。船頭が「女が乗っているから竜宮の神が怒っているのだ」と言われ仕方なく
幼子の尊敦(そんとん)(後の舜天王)のと妻の思乙(おみおと)を港におろし、日本に帰った。4年後、為
朝は八丈島で20余隻の船500余りの朝廷の兵に敗れ、切腹して死んでしまった。沖縄に残された思乙は
必ず帰ってくるという為朝との約束を信じて、今日帰るか、明日帰るか、と毎日待ち続けたがむなしく月日
が流れるばかり、二人が待ちわびた港、待港(まちなと)が 牧港 になった。
美里(沖縄市) → ・越来城の城下町、政治の中心地みさと(御里)が見里→美里になった。
宮城区 (北谷) → ・宮城区は埋立地。当初砂辺区に入れてあったが、1980年宮城として分離独立。埋め立て工
事にあたった企業の代表者の姓を取ったものである。なお、宇地原区、謝刈区、栄口区は小字
名からつけたもの。港区は漁港所在地から、北玉区は北玉小学校所在地からその名をとったも
のである。
山里 (沖縄市) → ・山内村と諸見里村の一部が合併したもの、山内の山と諸見里の里をとって山里にした。
山城 (石川市) → ・二千年前、山城三兄弟が村を開いた、それで山城という地名になった。
屋良 (嘉手納) → ・阿麻和利の出身地屋良城跡、ヤラムルチから来た。ムルチの水が、ヤーラヤーラ(静かに静
かに)たたえられたことから屋良となった。
国頭(クニガミ) → ・島の頭部にあたるので国頭
山原(ヤンバル) → ・土地の大部分が山林原野のため、耕地、村落も点々として稀にしか見られないから。
安波 (国頭村) → ・村を創って始めに住みついた人たちが、浦添の安波茶から来たので安波茶村からとって安波
とした。
運天(運天港) → ・源為朝が伊豆大島に流された時暴風雨が起こり、天を仰いで言った、「運命天にあり、余何ぞ
憂えん」と、数日後ある港にたどり着いた、その地を運天港と名づけた、という伝説から。運を天
にまかせてたどり着いた港
。
乙羽山 (今帰仁村) → ・北山城の按司を背負って(ウッパして)山を越えて逃げ延びた所。
田井良 (名護市) → ・水量が豊富で、ちょっと掘ると水が出る。井戸と田が等しい高さにあるといって田井良と名
づけた。
為又 (名護市) → ・この一帯は一面蘭草におおわれ、蘭又原(イタバル)といわれていた土地から。
汀間 (名護市) → ・昔、東方の汀間川と、西方の汀間田川が合流し、周囲は海水に囲まれ、汀の間に出来た部
落だったため汀間と名づけられた。
名護 → ・名護湾の凪(なぐ)、和やかな風光に由来する。
仲泊 (恩納村) → ・昔、名覇から名護へ行く時中間にあるこの地で一泊しなければならなかったので、仲泊という
地名がついた。
星窪・星田 (国頭) → ・昔、流星が落ちてくぼ地になり、そこを星窪といいその中央部は二百坪位の水田になって
いるので星田と言っている。、
万座毛 (恩納村) → ・尚敬王が国頭巡視の時、ここに立ち寄り、万人が座せしむべき景勝地だと言ったことから、
この地名がついた。
明治山 → ・1912年明治天皇の死去にともない、慈恵救済資金として七千四百円が割当てられ、県はそれを造林
資金に当てた。その山を明治山と名づけた。
世富慶 (名護市) → ・那覇から国頭に行く時、那覇を朝発って夕暮れ(ユックイ)にたどり着いたところから。
伊江島 → ・よい島、いい島の意味。
→ ・石の多い島、石島から石間(イシマ)。
|
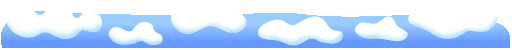



 トップページへもどる
トップページへもどる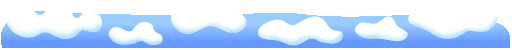



 トップページへもどる
トップページへもどる